Anatomage Tableの導入により、学生の理解度や学修意欲にどのような変化があったのか。実際に授業で活用されている先生に、教育現場での具体的な活用方法や学生の反応、導入の背景についてお話を伺いました。あわせて、受験生や保護者にも関心を持ってもらえるよう、オープンキャンパスでの活用についてもご紹介いただきました。
森ノ宮医療大学様
シミュレーションセンター長
朝倉 智仁先生

Anatomage Table活用した取り組みを紹介
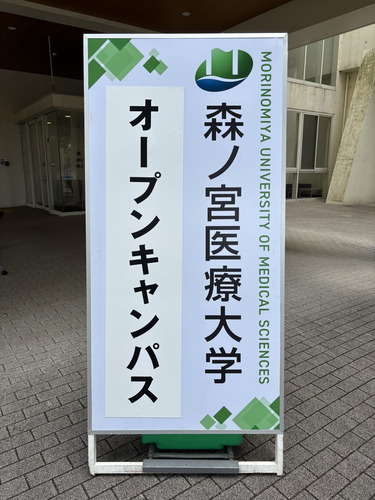

オープニング
Anatomage:本日、貴重なお時間をどうもありがとうございます。導入された製品、導入前の課題、選定のポイント、活用状況、導入の効果、今後の展望などを質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。
朝倉先生:こちらこそ、ありがとうございます。
導入製品
Anatomage:それでは、まず、今回導入頂いたAnatomage製品について、朝倉先生の方からご説明頂いてもよろしいでしょうか。
朝倉先生:はい、Anatomage Table Convertibleという製品を導入しました。解剖と言いますと徒手でご献体を系統解剖させていただくのですが、目的とする部位を見ていくということが、なかなか再現性が難しいということがありました。「いつでも一定のものを、しかも見たいところをクリアに見ることができるという解剖台があります」というお話を最初伺いました。本学のプロジェクトチームに入って実物を見させていただきました。私は系統解剖学というご献体を解剖させていただく研究を10年程行っていまして、それと比べるとやはり圧倒的にクリアに見えるということがありましたので、私はすぐに賛成をさせていただいたというところです。 しかも、それが 見たい方向から見ることもできたり、位置関係であったり、断面を見ることもできたりすることで、到底、ご献体を使っての解剖ではできない内容のものを再現できるということは、もう、この1台しかないなというふうには思っていました。
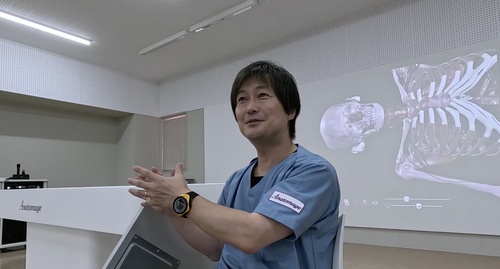
活用状況
Anatomage:今、どのような学部、学科に使われているのか、ご説明いただいてよろしいですか?
朝倉先生: 本学は3学部、8学科あるのですが、1年生で学科混成の授業があります。8人で1チームを構成して、シミュレーションセンター(T-MIC)で受講するというのがありますので全学科が使用しています。
Anatomage:シミュレーションセンター(T-MIC)についても簡単にご説明していただいてよろしいでしょうか?
朝倉先生:大きく分けると3エリアに分かれていまして、まず1つ目がディブリーフィングエリアと解剖学実習室という中で、ここにAnatomage Tableがあります。解剖が中心になり、ここで基礎的な医学の知識を身につけていきます。2つ目のスキルに関しては、後方のスキルスエリアのところで技術力をつけていきます。前方で基礎医学をしっかり学んでもらって、後方で技術をつけていく。そして、その知識と技術をもとにフィードバックしていく、貢献していくのは患者さんなので、そこで3つ目のICU(集中治療室)をイメージしたシミュレーションエリアがあります。高度シミュレーター機器を使って、例えば急変対応等の臨機応変な対応力を身に着けるトレーニングを行いますので、3つのエリアが連携している、というようなイメージでつくっています。


Anatomage:スクラブにロゴが入っているところがすごく目立つのですが、このライフサポート部について、背景と活動状況についてご説明いただいてよろしいでしょうか?
朝倉先生:もともとは少人数で1次救命処置の技術を身につけていくというクラブ活動だったのですけれども、ある時からファーストエイド、例えば絆創膏の貼り方から、普段の日常の中でよく起こる傷を手当てするといったことを学ぶようになり、徐々に部員が増えて、今150名を超える部員になっています。基本は1次救命処置を身につけて、かつ、AEDの普及活動がメインの部活動になっているのですが、2025年春にシミュレーションセンター(T-MIC)ができました。1次救命処置であるCPRという心臓マッサージをするのにも、「5センチの深さまで押しましょう」とか、「ペースはこうですよ」とか、消防局などの講習会で教えてもらうのですが、「なぜ5センチ押さなければならないのか?」そういったことを学ぶのにAnatomage Tableを部活動で活用させていただいています。「5センチ深く押した先に何があるのか?」、「どの部位に到達するのか?」といったことをAnatomage Tableを使ってイメージをつけて、そこからCPRをトレーニングすることができます。5センチ押さなければいけない理由をしっかりマスターすることで、CPRの質というのもどんどん上がってきているなというふうに感じています。コロナの影響で普及活動が止まっていましたので、これからはその技術を外に向けて普及活動が広がっていけばいいなと思っているところです。

Anatomage:部活動はどのくらいの頻度で行われているのでしょうか?
朝倉先生:毎週週一回に活動を行っています。毎週月曜日、夕方6時から7時までの活動で、内容はさまざまで、シミュレーションセンター(T-MIC)に設置している高度シミュレーターを使って部活動を行っています。
使用した反応
Anatomage:学生さんが実際にAnatomage Tableを使った反応はいかがですか?
朝倉先生:そうですね、1年生はまだイメージがついていなかったり、解剖学を学び始めたところですので、単純にすごいなという感想が一番多いです。2年生、3年生、4年生になってくると、ここを勉強するのに苦労したっていうのがよくわかっているので、Anatomage Tableを見ると、何でこれをもっと早く大学は入れてくれなかったのだろうか。みたいな反応が一番多いですね。見にくかったところ、複雑で覚えにくかったところをAnatomage Tableを使うと細かくイメージが付くので、大変良い学びになっていると思います。
Anatomage:今までAnatomage Tableを使用されていて、こういうふうに活用すると、これは面白いな、といった使用方法はございますか?
朝倉先生:例えば心電図検定という、学科の資格以外の取得を目指す学生さんもいますので、例えばAnatomage Tableで心臓を描出した場合、同時に心電図波形を現すことが可能です。その心電図を勉強するのがなかなか難しいのです。それをAnatomage Tableを使うと非常にシンプルでイメージが非常にしやすくて勉強しやすいというのを聞いています。自分の学科の資格以外の資格取得というところに活用できるというのは私も初めて聞きましたので、授業以外でそういう活用方法もあるのではないかなと最近感じました。
Anatomage:教える側として、効率が良くなった点や効果を感じる点はございますか?
朝倉先生:解剖学の授業資料を使いたいと思ったときに、それを1から作ることができるというのは我々にとって最大の魅力ですね。見せたいところを作り出すことができるということが一番大きく、他ではできないことなので、有効に活用させていただいているところかなと思います。
Anatomage: Anatomage Tableを導入して、学生への効果を感じられたことはございますか?
朝倉先生:そうですね 解剖学ってやはり難しい学問です。例えば地図を覚えていくような感じに似ていて、身体の部位の名前を覚えなければいけないのです。1年生から学修するのですが、覚える量も多くて簡単ではないため苦手に思われることが多い科目かもしれません。しかしながらAnatomage Tableを体験した学生からすると、解剖の面白さっていうのを、結構早い段階で感じてくれているみたいなので、教科書で見たものを、Anatomage Tableで再現してみたら「あ、こういうことだったのか」という理解が深まるというところから、解剖を嫌わないというような学生たちが今の部活動の中においては非常に多く見受けられるかなというところは感じました。

Anatomage:他の教員の先生方からのご意見等、フィードバックはございましたか?
朝倉先生:そうですね。まだAnatomage Tableを使用されている教員、学科に偏りがありますが、授業の中で積極的に活用されている先生もおりますし、特に理学療法学科になりますと、運動機能のところを扱いますので、その機能のイメージとして導入を検討していってもらってます。そうすると、やはり、触診に加えて画像での組み合わせで学ぶこと、エコー技術と合わせて活用することで、理解が深まるということは聞きました。今後さらに活用するためにはもっともっと我々教員側が勉強していく必要性があるなと感じています。
将来の展望
Anatomage:将来の展望というか、これを使って今後こう発展させたいといったイメージがあればお願いします。
朝倉先生:本学は正科の授業意外の講座をたくさん実施しています。現在、ライフサポート部の学生が中心でAnatomage Tableを使っていることから、扱える学生も増えてきましたので、そういった学生から発信する勉強会ができるといいなと思います。特に解剖学の知識を深めていくというのを教員から授業するだけではなくて、先輩と一緒に学ぶと案外内容がすっと入ってくることもあるかと思うので、そのような勉強会がもっと頻繁に行われるようになっていくと良いなと思います。
Anatomage:ありがとうございます。最後の質問ですが、今後、弊社に期待していることや、ご要望などお聞かせいただければと思います。
朝倉先生:いただいている 説明書を見て我々も使っていくということはもちろんできますが、例えば今日のオープンキャンパスだったら、こういう見せ方をするともっとわかりやすいのではないか、というようなシチュエーションに合わせて、こういうのを使ってみてはどうかみたいなのをお話しできる機会があると非常にありがたいなと思います。我々も今できる範囲内でしか 考えられていないので、さまざまなシチュエーションに応じてやれることはどんなことがあるのだろうかを知ることができると嬉しいです。今後はさらにAnatomage Tableの扱い方についての知識を深めていかないといけないので、使い方、見せ方として、何かアドバイスがいただけるような勉強会があると嬉しいなと思います。
Anatomage:本日は貴重なお時間とご意見をいただきまして誠にありがとうございました。
